電気ポットにポリエチレン袋を入れて調理するって?!
昨日、車で走りながら聞いていたラジオ。
防災の行事を和歌山のどこかでやったようで、その関連。
違和感を覚えたのでご紹介。
ポリエチレンの袋に牛乳と鶏肉と野菜を入れてシチューを作る話です。もちろん災害時に普通のクッキングができない場合を想定しています。
その袋を空気を出して封をして「電気ポット」に入れると言います。
電気ポット?
水を入れてスイッチ押して湯を沸かすポットかと思いましたが、どうやらひと頃流行った(今でも?)あの押すだけで湯が出てくるやつ、あれのようです。
余談ですが、私、あれきらい。常時保温しているなんてエネルギーの無駄でしょ?
ともかく、まず私が心配したのは、「袋、とけないの?」 ということ。
ダイソーで買ったうちの食品用の袋を見てみました。材質名ポリエチレンで、耐熱温度の表示なし、耐冷温度―30℃。
調べると、ポリエチレンの耐熱温度は低密度で70~90℃、高密度の方で90~110℃。あの電気式保温ポットの中って、100℃いってないんですか?
とけて、ポットの中に牛乳やチキンが泳ぐ姿を想像するとぞっとします。災害時というのは簡単に洗ったりできません。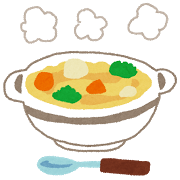
おまけに貴重な水も食材も無駄。
もうひとつ大きな問題は、電気あるんですか?ということ。
日本のインフラはオーストラリアよりいいような気がしますが、それでも災害が起こると、まず停電しませんか?
既に熱くなっていたお湯が入っているから、1回は使えるかもしれません。しかし、そんな貴重なお湯、普通に暖かい飲み物として飲んだ方がよくないですか?
冷蔵庫に残っていた牛乳と鶏肉を、停電で腐る前に使いたいと思ったのかもしれませんが。
おまけにちゃんと鶏肉に火が通るんでしょうか? 停電していなければそのうち?
でも、停電していなければ、わざわざこの方法を使わなくても…
私が住んでいる和歌山の田舎では、オール電化のお家以外は、たいがいLPガスで料理しているでしょうから、ガスはアウトで電気はOK、という状況はなかなか想像できません。
LPガスが使えなくなるのを心配するなら、あのカセット式のコンロとボンベを用意しておいた方が現実的でしょう。
ほんとの災害を想定できているんですか?と聞きたくなっちゃいました。この人にインタビューしていたアナウンサーも変に思ったかもしれませんが、話の途中で打ち切れないし… 気づいてなかったかも?
このイベントの続きで、テントをどのくらい早く立てられるかと時間を計っていました。災害の時、負傷者とかを、すばやく救助する必要はあります。もちろんすばやく逃げることはいちばん大事。
でも、一応安全になった状態で、時間を争うようにしてテントを立てる必要ありますか?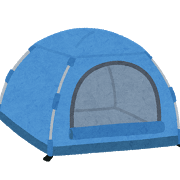
極寒の地なら命にかかわるかもですか? しかし、この和歌山で?
みんなのためにたくさん立てる必要がある自衛隊員とかならわかりますが、自分たちに割り当てられたテントを立てる時間は多少長くても実害なしでしょう。
競争というかイベントとしてはやりやすくおもしろかったかもしれません。
ただ、冬にテントをいただいても、その中では寝たくないですね。寒すぎる…


最近のコメント