日本語はシンプルではない
NHKの朝の連続ドラマ、あれれ、なんという題名でしたっけ? 「ひよっこ」でしたか。
九州のお饅頭が頭に浮かびますが、関東の茨城の話です。大阪には茨木というところがあります。
うちの4番目の子どもが、その茨木にいるのですが、このふたつを区別するのに、「いばらぎですか?」という人に、「いいえ、いばらき、です。大阪のは濁らないんです」と私は答えてきたのです。
ところが、えー?! 茨城も正しくは濁らないんですか?
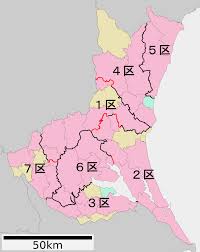
ドラマの中で、お母さんが突然行方不明になった夫を探してもらおうと警察に行って、やる気のなさそうな警官を前に、「いばらぎじゃなく、いばらきです!」というところがありました。
そうだったんですか。ということは、音では区別できないということです。大阪のいばらき、関東のいばらきというしかないですね。
しかし、このドラマの脚本の人、地元出身ですか? たぶん茨城の人が日頃思ってることなんでしょうね。
うちの実家のあたりは有田です。ありだと濁るんですが、(ねえ、にごりますよね、同郷のみなさん)九州にも有田があります。
有田焼で有名でしたが、こちらは濁らないで、ありたです。(そうですよね?)
近くに広川町という町があります。これはひろがわだと思ってきたのですが、これはもしかして、ひろかわ?
また、実家からもうちょっと山のほうに、修理川という地名があります。これをうちの祖父母や親はすりがわと読んでました。
ところが、街から来た人はしゅりがわと言います。私にとっては非常に抵抗感があるのですが。
うちの実家のお墓は岩間寺というお寺にあります。このお寺の名前は、いわまんじと、呼びならわしてきたのです。ところが、この間、たまたまネットを見ていたら、いわまじと書いてあるではないですか。
このお寺の属している浄土宗のサイトだったので、うーん、納得いかないけど、信じるしかないかというところです。
でも、この辺の人と話すとき、いわまじと言ったら、あんたいったいどこの人?って顔をされるでしょうね。
こういう問題は、日本語で使っている漢字が表意文字であって、表音文字ではないためです。漢字がなくて、ひらがなで全部書くことを考えると、ぞっとしますが、読み方という問題があるのです。
道路の標識についているローマ字表記、あれは、知らない土地に行ったとき、読み方がわかって本当にありがたいです。でも、あれを作るときには、ちゃんと地元の人に読んでもらわないと、間違いが定着する危険性があります。
列車のアナウンスとかでもおもしろいことがあります。
どうせ、生きている言葉は変化するものですけど、やっぱりひっかかる……


最近のコメント