田中光敏監督の講演を聞いた
昨夜、観光カリスマ講座というのを聞きに行きました。
場所は和歌山大学観光学部。観光に関係する各界の人に来ていただいてお話をうかがうというものです。
今回は今年の3回目でした。
1回目は観光庁のお役人、2回目はガイドブック「地球の歩き方」に携わった人、そして、今回は田中光敏という監督のお話でした。
映像をたくさん見せてくださって、時間のたつのを忘れました。
声がまた、深み柔らかみのあるいいお声で、こういう声で先生がレクチャーをしたら、学生はうれしいだろうなあと思いました。
監督は初めはCMディレクターだったそうで、その辺から観客とか協力者に訴えかける方法が自然に身についたのでしょうか。
最初の作品は「化粧師(けわいし)」、それから「精霊流し」「火天の城」「利休にたずねよ」「サクラサク」「海難 1890」と、日本各地の風景の中で作品を作っておられるようです。
私はどれも見たことがないのですが、探して、見てみたいです。
監督は映画のほかに、各地のプロモーションビデオも作っていますが、その制作にそれぞれの地元の人が大きな役割を果たしているようです。
彼によれば「観光における映像の存在とは、その町にいる人たちが主体的に動き出すに引き金になるものである」です。
どっかの制作会社に丸投げにしてそれで観光客を呼び込めるわけではなく、地域の人が積極的に地域のおもしろさを発見して宣伝しようと動き始めて効果が上がるわけです。
そりゃそうだろうと思いました。いくらきれいな景色を見せられて、訪ねて行っても、地元の人がしらーっとしていたら、たぶんつまらないでしょう。
話を聞いて、これって地域活性化の具体的な方法ね、と思いましたが、一朝一夕でできたわけではなく、何年もかけて、その気になる地元の人を増やして、その輪を広げて、結果が出ているようでした。
最後に見せていただいたのは、福井県の美浜町のプロモーションビデオでした。
台湾から観光に来てもらおうという趣旨で作った中国語のビデオです。
台湾の人口はどのくらいあるのかと思いましたが、そんなにどっとたくさんは来なくてもいいかもしれません。
私も、美浜というと原発、としか思いつかない人ですが、三方五湖の眺めは素晴らしく見えました。
そういうきれいなところに原発作ったのか、福島みたいに壊れたらどうすんの?と、沖縄の埋め立てにも心が飛んで、ちょっと憤りを覚えました。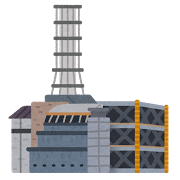
知らないと、何にもない寒村の海のそばだから作ったんだよねと何も感じないのですが。六ケ所村というのもありましたよね。
監督は、地元の人だと地元の具体的ないいところに気づいていないと言っておられました。外からの目で見る必要があるというわけです。
私の住んでいるあたり、それからもっと奥の方、まだまだ人が減るでしょう。私の目で見ると、四方山ばっかり閉塞的な空間です。
私など、山の方は集団移住したらいいんじゃないの、そしたら介護の効率化が図れるんじゃないの、などと乱暴なことを考えてしまいます。
それじゃいけないのかもしれません。
私はブリスベンに戻るつもりですが、あっちでも使えるかなとも思いました。だだっぴろい内陸部の村おこしなんていいかもしれませんね。村なんてなかったか…


最近のコメント