国旗に頭を下げるひと
この間、ある表彰式に行きました。
私が何かをいただくわけではなく、知り合いの子どもが賞をもらう機会でした。
親御さんの時間のやりくりがつかないということで、陰ながら応援に行ったのです。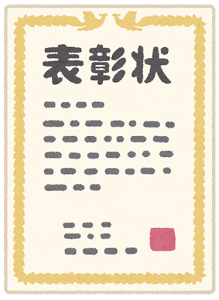
そこで印象に残ったというか、嫌な気分になったことがあります。
舞台の上に座っている主催者側や来賓の人たちが、席を立って正面の、あれなんというんでしょう? 演壇? あそこで受賞者に表彰状を渡しに行ったりする際、向こう側と自分の側の来賓もしくは主催者席に向かって礼をして、国旗にも斜めに立って礼をしました。
これです。
なんで、集まった私たちに向かって礼をしないのかなあと思いましたが、これは我慢することにします。ね、誰も集まらなかったら悲しくないですか? まあ受賞したのは中学生たちですから、ほうっておいても親や祖父母が集まるのでしょうが。
私が嫌だったのは「国旗に礼をした」部分です。
私は昭和20年代の終わりに生まれました。戦後の時代に育ったわけです。あの頃は、民主主義の台頭期で、学校では日の丸も見ず、「君が代」も歌いませんでした。
そういうことに対してはっきり学校や先生たち、だいたいの世間様がノーを表明していたのです。
小学校の卒業式には「蛍の光」だけで、「仰げば尊し」もありませんでした。
私はあの歌は好きです。一生懸命やってくれた先生に感謝しても悪くはないと思いますけどね。戦後だったので、戦争に加担したという意味もあって、先生たちが自分たち自身、襟を正すという気持ちだったのかもしれません。
また、その小学校では、役の軽重ができる学芸会はなく、その代わりに音楽会でした。ただ、音楽会でも実は平等にはならないんです。ハーモニカの子と、アコーディオンなり木琴にあたった子は違います。
下の学年でしたが、バイオリンを習っている子がいました。
当時でもピアノを習っている子は結構いたのでしょうが、田舎だったから、バイオリンなど400人ほどの全校児童で彼女だけでした。
その彼女にその普通の音楽会でバイオリンを弾かせたのです。独奏ではなく、その学年の合奏の中でだったのでしょうが。独奏部分があったのかなかったのか、どんな音だったのか、忘れましたが、私にとっては非常に記憶に残るできごとでした。
これって、平等な扱いじゃないです。私はその他大勢のハーモニカか縦笛でしたから。
もしかして、私が子どもたちにチェロやバイオリンをやらせたのは、この記憶が糸を引いていたのかもしれません(笑)。
ただ、オーストラリアでは普通の小学校やハイスクールで、そういう機会があります。小規模ながらオーケストラやブラスバンドとかがあります。
どの子も機会均等です。ただ、親がさまざまですから、やらそうという親とやめとけという親がいて、する子としない子ができます。
さて、日本のそういう「反軍国主義で平等な」小学校で、先生の言うことをよく聞く優等生!だった私としては、日の丸に礼をしている姿というのは非常に違和感を覚えるのです。
この反動・右傾化のご時世ですから、正面に日の丸がぶら下がっているのはよしとしましょう。でもちゃんとピンと張ってなかったんですよね、この日の丸。
たるむとほんとカッコ悪い。次の機会には真ん中がたるまないように張ってくださいませ。
しかし、振り返って、私、オーストラリアの国歌、Advanced Australia Fair 好きです。それからその前に使われていた、God save the Queen もいやじゃありません。オーストラリアは正式にはまだイギリスの下にあります。独立していないんです、形の上では。
オーストラリアの国旗もいやじゃありません。イギリスの国旗に南十字星をつけたものですが。
日本の軍国主義、帝国主義に比べれば、大英帝国の所業、悪行の方がずうっと長くずうっと規模が大きかったのではないかと思いますが。
どこから来るんでしょう、この気持ちの違いは。舶来崇拝? 小学校の時の民主教育に素直過ぎた私? まだオーストラリア国民になっていないから?
ともかくいやだー あれが通例なら、日本の表彰式、見に行くのやめまーす!


最近のコメント